
こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。今回は発達障害の子供にたいする家庭学習についていただいたお便りをご紹介します。
発達障害のお子さんであっても、知的障害のお子さんと異なるのは発達に個人差があるだけで、教えたことがしっかり身につくということにあります。
家庭学習においては、お子さんが欠席することも遅刻をすることもありませんから、お子さんのペースに合わせて学習するのが利に適っています。
連絡帳には先生からのその日のお子さんの行動、学力レベルについて明記してもらっておけば、家庭学習で足りない部分を補うだけで学校での学習とのバランスが取れます。
例えば苦手だったリコーダー、毎日家で練習していれば、その成果が表れているようでお子さんも嬉しくなるでしょうし、クラブ活動にも積極敵に取り組むことになるかもしれません。
そのまま充実した学校生活を送ることもできますし、家庭環境を変えなければならない不安も少くなるでしょう。
発達障害のお子さんの場合、じっとしていられない、集中力が途切れがちであるケースも少くないようです。
ですから、家庭学習が習慣にならない不安になるかも知れませんが、毎日やることに意味があります。
また計算ドリルを毎日やるのが習慣になって、算数に自信がついてくることもあります。
中には、親子で反省ばかりしてしまうケースもありますが、発達障害の家庭においては健全者とは少なからず違うので、反省ばかりというのは日常茶飯事です。
前向きな気持ちでいる時間を多く割きましょう。
家庭学習では、指導方法に不満があったり、お子さんにつらくあたることもあります。
お子さんの学年が上がると気になるのが、担任の先生の評価です。
家庭学習ならば、相性抜群の親子で取り組むこともできますが、性格的に相性が悪いこともあります。
これは担任の先生だけでなく、家庭教師を雇うことになっても同じです。
やり方はそれぞれ、いいところを探したり、いい面を見るようにしましょう。
それでも家庭学習で悩む場合、学校に相談したり、家庭訪問・個人面談などをお願いしてみましょう。
発達障害のお子さんの場合、学校生活に影響が出るようであれば先生方に理解をしてもらいましょう。
家庭学習とはいっても家庭内だけで問題を解決することは難しいでしょうから、教育機関、地域住民とも連携を取りましょう。
ときに、児童館などが利用できるケースもあります。
宿題を見てくれるボランティアの方々がいますし、苦手な科目を教えてもくれますから、息詰まることがあったり缶詰め状態でストレスが溜まるようならば、ときにリフレッシュさせるために異なる環境に身をおくのも手の内です。
「この子もがんばってるよ」と声をかけるようにすれば、やる気を感じるかもしれません。
お子さんは褒めて伸ばせといいますが、特別にすごい成果を上げなくても、きちんと学習をすることが周囲から認めてもらえるようになれば、勉強にやる気を感じるようになるかもしれません。

私もグレーゾーンですが「褒められる」とやる気が出て、怒られる(叱られる)とモチベーション駄々下がり‥という過ごし方をしてきました。とにかく「褒める」という学習方法は全くの同感です。
✅ こちらも参考までに
➝発達障害の中学生にすすめたい「支援専門家監修」のタブレット学習

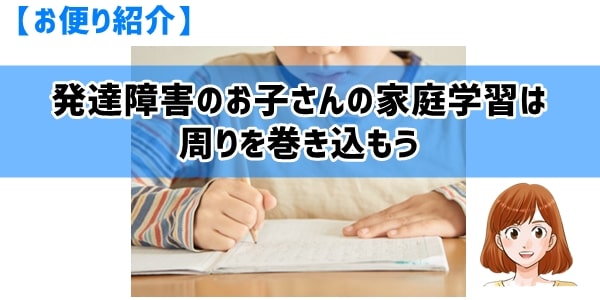

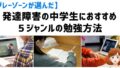
コメント