発達障害の中学生に多いのが”勉強をすぐに忘れる”ということ。

私もグレーゾーンで育ってきましたが、なかなか覚えられず勉強した内容をすぐに忘れていました。
そんな実際に育ってきてわかった知識と発達障害コミュニケーション指導者の資格を勉強した経験から、発達障害の中学生が勉強を忘れる3つの理由とおすすめの対策方法についてご紹介します。
- 発達障害の中学生が勉強をすぐに忘れるのは何で‥?
- 本当の意味で勉強をわすれない、おすすめの対策方法が知りたい‥。
そんな疑問をきっと解消できるかと思います。
発達障害で勉強を忘れる3つの理由
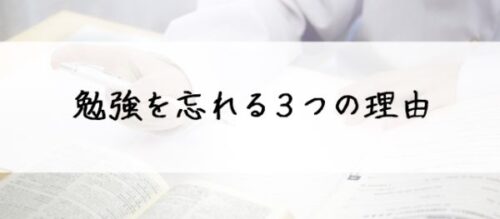
発達障害で勉強を忘れるときに、考えられる原因がつぎの3つです。
- 「楽しさ」が感じられず興味を持てていない
- 本当の意味で解き方など「理屈」を理解できていない
- 勉強中に別のことへ気をとられている
この3つの原因について詳しくお話しします。
理由①「楽しさ」が感じられず興味を持てていない
発達障害の中学生が勉強をすぐに忘れる1つ目の理由が「楽しさ」です。
この「楽しさ」というのは発達障害のある子供にはとくに重要で、まずもって備わっていないと何も始まらない感情になります。
私もグレーゾーンで育ってきて、実際に興味が惹かれないことにはまったく関わらなかったという経験をしてきました。
勉強に「楽しさ」がないと子供はどうなるか?についてもう少し詳しくお話しします。
①-1:やる気が出ない
まず勉強に限らず、すべての物事において「やる気」が出ません。
いくら周りから勧められたところで、本人が興味をそそらなければまずそれに対して取り組むことはありません。
逆に”もしかしたら楽しいかもしれない”と何となくでも感じることが出来れば、チャレンジ精神旺盛な発達障害の子供が興味を向けるキッカケとなります。
私が実際にそんな経験をしてきたので間違いないです。
したがって「楽しいかも‥」と思わせることが、やる気にさせるためには大切です。
①-2:覚えるという気持ちがもてない
勉強に「楽しさ」が感じられなければ、当然ながら覚えることはできません。
そのそも”覚える”という思考が頭の中に存在しないため、いくら勉強をしてもすぐに忘れることになってしまいます。
私も勉強が嫌いでその時間を早く通り過ごそうと考えて、聞いている素振りをして実はまったく理解していなかった経験があります。
学校の先生に親とともに呼び出されて”IQはクラスで3番目以内なのになんで成績が悪いのか?”と問いただされて親も返答に困ったということが実際にありました。
そのときの私の感じとしては、授業中にしっかりと黒板の方を向いているけど頭の中はずっとほかのことを考えているといった状態。
したがって勉強を忘れるどころか、まったく覚えることもできません。
学校の授業に「楽しさ」を感じることが出来なかった、という表れです。
①-3:自分がやるべき事というのがわかっていない
勉強をすぐに忘れる・覚えないという裏には「自分事として腑に落ちていない」ということが挙げられます。
将来的に勉強がすべて自分へ返ってくることを理解できておらず、どれだけ勉強に”重要性”があるのかが分かっていない状態です。それどころか「勉強分からないのにそんなにイジメないで!」という気持ちさえあったりします。
この状態が続くことによって起こるのが世間に対する反発です。
まわりの同級生たちは成績が上がっていく中で、自分だけは勉強というものを理解できていないためどんどん孤独感が強くなっていく。
この状況を克服するために必要なのは、
勉強の楽しさよりも「将来の楽しみ」を理解させること。
こんな勉強をすれば、こんな楽しい将来が待っている。
そんなふうに将来について一緒に理解をする、という対策が重要なポイントになります。
そのまま放っておくと悪化する一方です。
理由②本当の意味で解き方など「理屈」を理解できていない
発達障害の中学生が勉強をすぐに忘れる2つ目の理由が「理解していない」です。
基本的に勉強全般に対しては”楽しさ”を感じていませんが、自分が興味の持てる教科や分野だけは率先して覚えようとします。もしそんな教科や分野が見つかればラッキーで、まずその部分からしっかりと理解させてあげることが大切です。
しかし、しっかりと理解したいのに理解に辿り着くことができない。
そんな勉強方法ではせっかく興味を持てたのに「分からないから嫌」という感情が増えてきて、次第にその教科や分野まで嫌いになってしまいます。
自分から「楽しさ」を感じることが出来るというのは貴重なので、もし興味を持てた場合はしっかりと理解に辿り着く勉強方法を与えるのがおすすめです。
ただし難しく文字ばかりが並んでいるような「楽しさ」を感じない勉強方法では逆効果になりますので、くれぐれも見た瞬間に「楽しそう!」と燃える勉強方法を与えることが大切です。
理由③勉強中に別のことへ気をとられている
最後にお話しする理由が「散漫」です。
勉強をすぐに忘れるというのは頭に入っていない証拠なので、いってみれば”集中できていない”ということです。
集中できていない理由としてもっとも大きいのが「勉強をする環境」になります。
私も勉強をするとき周りに興味を惹かれるようなものがあると、そっちばかりが気になって勉強に集中することができませんでした。
健常児であれば”勉強中だから‥”と気を向けることは少ないと思いますが、発達障害があるとすぐに「興味がそそられる=楽しい」という方向へと気が向いてしまいます。
その結果として、せっかく興味を持って取り組んだ勉強内容をすぐに忘れる。
これも非常にもったいないので、勉強をする環境は「何もない」くらいがちょうどいいです。
勉強をすぐに忘れる発達障害の子供へおすすめの対策
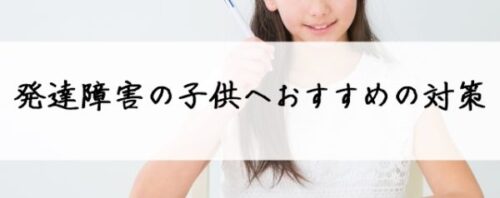
では、どんな勉強方法であれば「楽しさ」を感じられるか?について。
発達障害の中学生が勉強をすぐに忘れる、根本的な原因が「楽しさ」が感じられないことです。
楽しさが感じられないことが全ての要因となっているのであれば、発達障害の子供が楽しさを感じることのできる勉強方法を実践することが問題解決へとつながります。
発達障害の学校外学習を考えてみるとこうなります。
| 学校外学習の種類 | メリット | デメリット |
| 学習塾 | 効率良く教えてくれる | 障害によっては通塾が困難な場合があり学校と変わらないので楽しさを感じない。 |
| 家庭教師 | 子供に合わせて指導がされる | 発達障害を理解していないことが多い |
| 親が教える | 子供が自然体で勉強できる | 親の方が教え方を分からない場合がある |
| 通信教育 | ・ネット教材は理解しやすい ・子供のペースで勉強できる ・楽しさの工夫が多い ・ご褒美などがある | 紙教材では限界がある |
学習塾
学習塾はどうしても”通塾”があるため、障害の度合いによっては通えない場合があります。
また発達障害があると受け入れを拒否されることも多く、実際に通わせても学校とあまり変わらず「楽しさ」を感じることができません。
私も学習塾に通っていた時期がありましたが、通わせれば何とかなるというものではなく「まったく勉強をする気にならず成績は変わらなかった」という経験があります。
家庭教師
家庭教師は自宅で取り組めるので便利な方法ですが、問題は対人関係です。
子供自体が対人を苦手としていればやめたほうがいいですし、実際に来てくれる講師との相性も考えておかなければいけません。これをクリアできるのであれば家庭教師も良い選択です。
親が教える
親が教えるのはもっとも良い勉強方法になります。
ただし発達障害の特性をしっかりと理解をして、子供がわかるように理屈を説明できるか?というのが大きな問題として挙げられます。
実際に私の親も勉強を教えてくれましたが、あまりにも理解しないので声も大きくなっていき、しまいには怒られながら勉強をすることになりました。しかし怒ったところでどんどん勉強をイヤになるばかりなので、その方法は絶対にやってはダメです。
発達障害のことを理解した教え方、これができれば親が教えるのがベストです。
通信教育(ネット教材)
最後に通信教育という方法がありますが、私はこの方法が全ての問題を解消できるもっともおすすめな勉強方法になるのかなと思います。
紙教材では問題解決に至るまでにならない場合が多いですが、ネット教材を選べばキャラクターなどが動くことによる「楽しさ」が備わっているため取り組みやすい方法です。
さらにネット教材を漠然と選ぶのではなく、発達障害の特性に沿って作られたものであればベストです。私がおすすめの「発達障害支援の専門家によるネット教材」がありますので、ぜひ目を通してみてください。
発達障害の中学生が勉強を忘れる3つの理由と対策まとめ
ここまでをまとめます。
発達障害で勉強を忘れる3つの理由
- 「楽しさ」が感じられず興味を持てていない
- 本当の意味で解き方など「理屈」を理解できていない
- 勉強中に別のことへ気をとられている
勉強をすぐに忘れる発達障害の子供へおすすめの対策
➝通信教育(ネット教材)
これで「発達障害の中学生が勉強をすぐに忘れる」という問題の解消につながります。
何度もいいますが、勉強を忘れるのは”楽しさ”が感じられないから。
そのためにはパッと見た瞬間から「楽しそう!」と思えるような勉強方法を与える、さらに発達障害をよく理解した教え方のできる方法。
これをしっかりと実践すれば、きっと勉強を忘れることも減るのではと思います。
人気記事

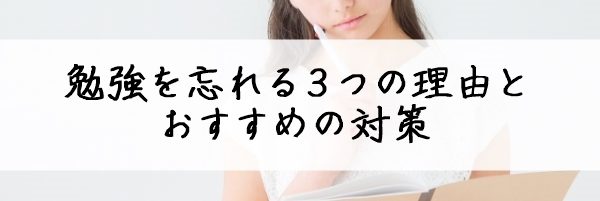
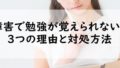

コメント