
こんにちはゆっきーです。今回は「発達障害で勉強についていけない」という悩みを解消につなげるための情報をお伝えします。
発達障害の中学生が勉強についていけない原因は、まず障害による「学力低下」が考えられます。
さらに勉強へ取り組むための「要素」が揃っていることで、勉強についていけない問題を解消につなげることが期待できます。
この2つの問題を解消するため、
- 発達障害の中学生が勉強についていけない場合におすすめの家庭学習
- 発達障害で勉強についていけない場合の改善策
について、私もグレーゾーンで悩んだ経験から詳しくご紹介します。
発達障害で勉強についていけない場合におすすめの家庭学習


勉強についていけないということは理解が追い付いていないということです。そこで重要になるのが「学力に見合った勉強内容」「ムリのないペース」になります。
理解が追い付かないという問題を解消するには、理解できる範囲までさかのぼること。
さらに子供の精神的な部分ではなく学力低下というのは発達障害の特性が原因となっているので、ムリのないペースで少しずつ学力を上げて勉強についていける方法を考えることが大事です。
私も中学生時代にはグレーゾーンのため勉強についていけない状態が続きましたが、その経験があるからこそここで紹介する3つの勉強方法がおすすめと感じます。
無学年制のネット教材を使ってみる


発達障害の中学生が勉強についていけない場合、もっともおすすめと感じる家庭学習が「無学年制」で取り組めるネット教材になります。
ネット教材というのは一般的に「いまの学年しか選べない」とか、または「1つの学年しか選べない」という部分がネックになって発達障害の中学生には向いていないと思います。
しかしネット教材の中でも逆におすすめなのが「無学年制」によって勉強できる教材で、学年を自由に選んで取り組めるため学力低下問題の解消が大きく期待できる家庭学習になります。
そんな無学年制のネット教材で、私がもっともおすすめなのが「すらら」です。

| 取り掛かり | 問題解消 | 継続 |
| 楽しさが十分に感じられる ★★★★★ | 無学年制 ★★★★★ | アニメーション授業 ★★★★★ |

この「すらら」というネット教材は普通の作りではなくピッタリの勉強ができる「無学年制」にプラスして「発達障害支援の専門家」が監修しているため本当の意味において子供が理解できる作りとなっているのが大きな特徴です。
画面構成はすべてイラストで楽しさも十分に感じられるし、さらにアニメーション授業で話しかけるように教えてくれるため、勉強への取り掛かり~継続まで本当の意味で問題解消へつながる家庭学習になります。
発達障害で勉強についていけない中学生、またその家庭にもっともおすすめといえるネット教材。
もしこの勉強方法でダメだったら、ほかでもダメだと私は感じます。
私も発達障害の中学生とって根本的な問題解消につながる勉強方法をいろいろ探ってきましたが、このネット教材「すらら」はもっとも理想形に近い教材だと思います。
無料体験も出来ますので、ぜひ一度ためしてみてください。
私のレビュー:発達障害のある中学生にすすめたい支援専門家監修のタブレット学習
オンライン家庭教師を利用してみる


発達障害で勉強についていけない中学生へ、つぎにすすめたいのが「オンライン家庭教師」という自宅学習のスタイルです。
学年関係なく取り組めるのでいちばん大きな学力問題をカバーできて、しかも人と接することが苦手な場合でも画面越しにやんわりと慣れることが期待できるためおすすめの勉強方法です。
オンライン家庭教師の中には教材の高額販売などをおこなう悪徳商売をする会社もありますが、運営内容までしっかりと見極めれば安心して取り組める自宅学習になります。
とくに発達障害があることでオンライン家庭教師から断られる場合も実際にありますが、その中でも間違いなくおすすめなのが「インターネット家庭教師Netty」になります。

| 取り掛かり | 問題解消 | 継続 |
| 楽しさが感じられる ★★★★☆ | 無学年制 ★★★★★ | 発達障害を理解した指導 ★★★★★ |

この「インターネット家庭教師Netty」というのは母体となるのが家庭教師ノーバスという会社。こんな感じで発達障害支援にとても力を入れています。
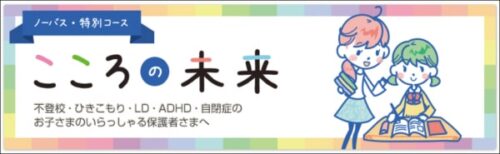
家庭教師ノーバスは全国的にも珍しい「発達障害の理解に力を入れている会社」として有名で、首都圏だけが派遣エリア。このオンライン部門のNettyを利用すれば全国どこでも発達障害を理解した指導を行ってくれるので、安心して任せることができます。
使用する教材などもいたって自由なので、ふだん使って勉強しているテキストなどでもOKです。
一般的なオンライン家庭教師では講師陣も発達障害に対する教え方がわからないためチグハグになりがちですが、ここなら間違いなく理解につながる指導が期待できるため勉強についていけない中学生にはおすすめです。
参考:発達障害の中学生「家庭教師ノーバス」を選んで損しない7つの理由
気分を変えて英会話を勉強させてみる


グレーゾーンの私が、中学生に進級したとき楽しみだったのが「英語」でした。新しい何かがはじまると思ってワクワクしていたのを思い出します。
極論ということではなく1つの方法論として、発達障害で勉強についていけない中学生へすすめたいのが「英会話」です。私のように新しいことが始まるワクワク感をもって学習意欲が湧くよい方法になります。
発達障害で基本教科もついていけないのに、英会話なんてとてもムリ‥?
いえ、まったくそんなことはありません。私が中学生に上がったとき小学生時代になかった「英語」が始まることでワクワクしたように、新しいことが始まると気分も一新できるものです。
したがって気分を変えて「オンライン英会話」を学んでみるというのも1つの方法で、ここから学習意欲が湧いて勉強に集中できることも十分に考えられます。
自粛対策にもおすすめといえるオンライン英会話はたくさんありますが、その中でも私が発達障害の中学生にもっともおすすめなのが「学研Kimini英会話」になります。

| 取り掛かり | 問題解消 | 継続 |
| 楽しさが感じられる ★★★★☆ | 豊富な無料テキスト(無学年) ★★★★★ | イラスト多様の予習・復習動画 ★★★★★ |

学研という会社自体が発達障害をはじめ不登校などについて理解があるため、ほかのオンライン英会話を選ぶよりもピッタリの指導が受けられます。
学年や学力関係なくどのコースでも選べるのでピッタリのレッスンができて、しかも予習・復習動画があるため継続にもつながりやすいのが特徴です。
テキストはすべて無料で用意されていますがボリュームがとても多く、学力に見合った内容のレッスンを受講することができるのも学研の大きな特徴といえます。
講師はすべてフィリピン人なので慣れるまでにやや時間がかかるかもしれませんが、勉強についていけない中学生にとってはまた違った風が吹いて新鮮な気持ちで勉強できると思います。
ちょっと気分を変えてみる、というオンライン英会話の利用もまたおすすめの方法です。
レビュー:学研kimini英会話の中学生における効果・口コミなどを徹底レビュー
発達障害で勉強についていけない場合の改善策


グレーゾーンの私も、中学生時代は勉強についていけないことで悩んでいました。そんな辛い経験からわかった改善策がココでご紹介する3つの項目です。
- 【取り掛かり】まずは「楽しさ」を感じられる勉強方法を考える。
- 【問題解消】いまの学力に「見合った範囲」の勉強をさせる。
- 【継続】文字ばかりではなく「イラスト」などが多用された学習教材を考える。
この3項目というのは、先ほどご紹介したおすすめ勉強方法の根拠でもあります。
さらに詳しくこれら項目について解説をしていきます。
【取り掛かり】まずは「楽しさ」を感じられる勉強方法を考える


発達障害で勉強についていけない中学生というのは、共有して見られる特徴が「学力低下」です。
学力低下が起こってしまう主な原因に「障害特性による集中力の欠如」「楽しいと感じられない勉強方法」という2つが考えられます。
グレーゾーンの私もそうでしたが、集中力の欠如というのは自分でどうしようも改善できませんでした。
頭の中でいろんなことがグルグルと回って、いわゆる「2つ3つくらいのことを同時に考えてしまう」という状態のため集中できないという感じがもっとも近いかと思います。
この頭の中で複数のことがグルグル回るというのは発達障害の特性ですが、そうなってしまう原因というのも存在します。これが「楽しさを感じない勉強方法」です。
私の場合は学校の授業をまったく聞くことができませんでしたが、先生には悪いですが「授業が感じられない」というのが大きな理由。楽しさを感じられないので余計に頭の中で違ったことがグルグルと回ってしまい、結果的に勉強へついていけないという悪循環に陥ってしまったと実体験から感じています。
そこで私が、発達障害で勉強についていけない中学生へまず重要と思うのが「楽しさ」です。
何はともあれ「楽しさ」がなければ勉強をやる気すら起こらず、いくら勉強は大事とはわかっていても一向に頭の中で2つ3つほかのことを考えてしまい勉強が手につかない状態。つまり「集中力の欠如」につながっていたというわけです。
したがって、まずは勉強に「楽しさ」を感じられることが大事。
この部分をクリアしないと勉強をスタートすることすらできないので、ほかのことよりも初めに考えるべき項目がこの「楽しさ」になります。
【問題解消】いまの学力に「見合った範囲」の勉強をさせる


私が中学生時代にもっとも辛かったのが「勉強についていけてないのに問題を解かせられる」ということでした。
これは本人じゃないと分からないかもですが、本当につらいです。
だって勉強についていけてないから理解できないのに、さらに難しい先の部分を解かせようとするんですから。そんなの解けるわけがないです。
せっかく「何だか楽しそう」と感じて勉強をスタートできても、自分の学力に見合った範囲に取り組まないと理解できずまったく面白くないため、ただ辛いだけになってしまいます。
そこで重要なのが「学力に見合った範囲」を勉強させること。
問題を解けたときはやはり嬉しいもので、発達障害というのは極端なので「1つ解けるともっと解いてやる!」と思うものです。私が実際にそうでした。
決して無理をさせず解ける範囲の問題を与えるというのは改善策としてかなり効果的で、発達障害の「興味を持ったらとことん集中する」という特性を逆に利用することにつながるため大きなポイント。
ここで崩れてしまうとかなりもったいないので、無学年制で勉強できる教材などを利用してズレのない範囲を取り組ませることが大切です。
ポイントは「無学年制」という部分です。
【継続】文字ばかりではなく「イラスト」などが多用された学習教材を考える
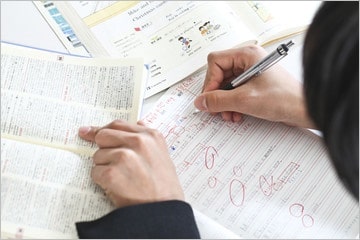

楽しさを感じて勉強をスタートできて、さらに問題が解けることの楽しさが分かってくる。そこでもう一歩として大事なのが「継続」につなげることです。
ここまで良い循環で勉強をさせることに成功すれば、あとはいかに「継続」へつなげるかが問題です。
この継続にまでつながれば「勉強するための3項目」をクリアできるので、発達障害で勉強についていけない中学生がグンッと学力を伸ばす大きな転機となることも十分に考えられます。
ここが大変身できるかどうか、に関わってくる大きな瀬戸際じゃないかと私は思います。
そこで継続につなげるため重要なのが「文字が多すぎない」という部分です。
勉強をやる気になっている間は、文字が多いのは一向に構いません。
文字の多さなんて乗り越えてでも問題を解けるようになるぞ!と思っているので一定期間は大丈夫ですが、さすがに疲れてくると文字の多さによって勉強のやる気を損なってしまう可能性が考えられるようになります。
つまり、せっかく「勉強に集中できていた波に乗っていた」のに継続が途切れてしまうということ。
あくまでも目で見たときの楽しい雰囲気はある程度残しながら、少しずつ文字数が増えていくような勉強方法によって文字に慣れていくスタイルが好ましいと私は感じます。
とくに一気に文字ばかりの勉強方法へ変えるなどは決してやらないほうがよくて、どこかに楽しさを感じられるポイントを残しながら少しずつステップアップしていくことが継続するための超重要なポイントになります。
もし無学年制のネット教材で勉強をスタートさせたのであれば途中で変えることなく、ずっと同じ教材を使って同じペースで勉強できるような環境にした方がおすすめです。
このような「勉強するための3項目」がうまく回れば発達障害で勉強についていけない中学生が大変身を遂げることも十分に期待できますので、ぜひ実践してみてください。
まとめ

今回は「発達障害で勉強についていけない中学生」へ向けておすすめの勉強方法や、親の家庭学習への取り組み方(改善策)などをお話ししてきました。
いずれもグレーゾーンの私が実際に経験した、学生時代のつらかった思い出がベースになってます。
自分ならこんなふうにやればきっと勉強できたんだろうな、という想い。
私も知能指数はめっちゃ良かったみたいですが、集中力が散漫で勉強に取り組むことができず成績もずっとわるい位置で成長してきました。
くれぐれも、私と同じようにならないでください。
発達障害があるから勉強できないと思うのは、まったくの大きな間違いです。
勉強をやる気にさえなれば人が変わったように急成長する可能性を十分に秘めていますので、いま勉強についていけないと感じても諦めてしまうのは最高に愚策です。
そのためには勉強をする環境をまず整えて、発達障害の特性をよくよく見つめながら家庭学習を考えることで「子供の大変身」を遂げる可能性を持てるようになります。
まずは「楽しさ」から始めて、つぎに「無学年」でピッタリの勉強をさせる。
最後は文字ばかりで退屈にならないよう「継続」につなげることで、良い勉強サイクルにつながります。
ぜひ良い方向へ進むよう私も期待しています。




コメント