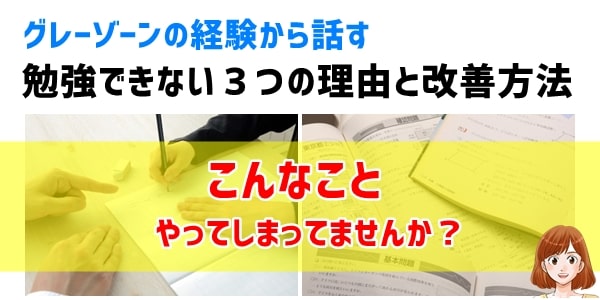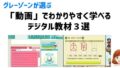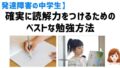こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。
- 発達障害の中学生が勉強できない‥
- なんでうちの子は勉強できないんだろう‥
そう思われる原因は大きく「3つの理由」が考えられ、私もグレーゾーンで同じような経験があることから子供が勉強できない気持ちはよくわかります。
そのまま放っておいても、まず一向に勉強できるようにはなりません。
一刻も早く原因を取り除くことが最良の手段になるので、原因と改善方法について手早く解説していきます。ぜひ家庭環境などをもう一度見直してみてください。
家庭環境が良くない


発達障害の中学生が勉強できない場合の、もっとも大きな理由としてまず「家庭環境」が挙げられます。
私の家庭もこの家庭環境が悪かったことで、まったく勉強をする気持ちにもなれませんでした。
家庭環境の悪さというのは、おもに両親の喧嘩などによるもの。
とくに子供の前で大きな声を出して喧嘩をするなどはもってのほかで、子供心では恐怖心と不安などが入り混じってとても勉強をする気にさえならないものです。
勉強よりも「どうすれば両親が喧嘩をしなくなるのだろう‥」「もっと楽しく暮らしたい‥」という悪い家庭環境の解決策ばかりを考えてしまい、まったく勉強できない状態に陥ってしまいます。
発達障害の中学生というのは、思った以上に繊細で敏感に家庭環境(空気)を感じ取っています。
両親の喧嘩(仲の悪さ)だけではなく、子供が自宅で勉強しやすい環境であるかをしっかりと考えることが何よりも改善方法になります。

私の両親も毎日のように喧嘩をしていて、目の前でも関係なく大きな声を張り上げてお互いが言い合っていました。
とても勉強できる環境ではなくなりますよ。
自分の部屋にこもっても大きな声が聞こえてくる始末で、まったく勉強できない環境です。
笑い声であれば勉強できない状態にはなりませんが、喧嘩をする声というのはうるさいだけではなく「不安と恐怖」を感じさせていることを親として自覚しなければいけません。
さすがに物を投げる音が聞こえたときは、あまりの怖さから仲裁に入ることもありました。
こんな子供に恐怖を与えるような勉強できない環境を作ってしまうのは「本当に子どものことを考えていない」という部分から起こるのではないでしょうか。
その後は両親が別居をはじめたため喧嘩の場面を見ずに済みましたが、別居すれば勉強できるというわけではなく寂しさから勉強できない状態は続きます。
結局、家庭環境の悪さというのは勉強できない環境を引き起こします。
本当に子どものことを考えれば、家庭環境を悪くするといった発想はなくなるのではないかと思います。
文字ばかりの教材を使っている
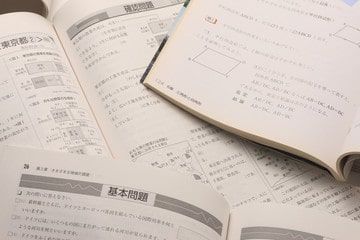

もし家庭環境が良くても「勉強に使う教材」が原因となっている場合も考えられます。とくに文字ばかりの教材は要注意です。
とくに発達障害の中学生というのは、文字ばかりの教材を与えられ勉強しなさいといわれても難しいもの。文字を理解するだけで疲れてしまうので、ほとんど勉強できない状態に陥ってしまいます。
文字を理解するのが難しいというのは「文字から理屈を読み取る」「理屈をつなげる」という作業にとても時間がかかり、スムーズな勉強ができない状態。
できればイラストでわかりやすく理屈が理解できるような工夫があったり、音声や動きなどでより理解しやすい教材であるほうが勉強しやすく腑に落ちやすい環境作りになります。
もし文字ばかりの教材を使っていれば、再度教材内容をチェックしてみることも1つの改善方法です。

私の中学生時代も「文字ばかりの教材」を与えらてたことがありましたが、文字を読んでもまったく頭に入らず勉強できないという経験があります。
よほど集中できる整った精神状態で、さらに勉強に対してやる気がある場合はまだマシ。とくに自分から勉強しよう!と思わない限り、文字ばかりの教材では勉強できません。
発達障害のある中学生というのは、文字を読んで理解するというのがとにかく苦手です。
できれば内容を噛み砕いて、わかりやすく教えてもらうほうが理解できます。自分で文字を読んで理解して、さらに理屈を読み取るという作業はとにかく難しいのが発達障害の特性になります。
もし教材を考えるのなら、文字ばかりではなく「イラスト」などでポイントが掲載してあるなど。
またパソコンやタブレット端末で勉強できる通信教育(ネット学習)などは、映像授業が搭載されて文字を読む代わりにわかりやすく説明してくれるなどが効果的な改善方法です。
✅ こちらを参考までに。
発達障害のある中学生にすすめたい支援専門家監修のタブレット学習

子供のペースを乱している


とくに家庭学習しているとき闇雲な口出しというのは子供が理解するペースを乱すため勉強できない原因につながります。
発達障害の中学生というのは、とにかく「自分のペース」で理解させることが重要です。
がんばって一生懸命に考えて理解しようとしてるとき、ペースを乱されるような横槍を入れてしまうとまったく勉強できない状態になってしまいます。
自分のちからで理解しようとしているときに横槍が入ってしまうと、今まで頑張っていたことが全部「無」になってしまうような気がして、その後は勉強のやる気すらまったく起こらなくなってしまいます。
とくに注意してほしいのは「まだ出来ないの!?」「なんでわからないの!?」という言葉掛け。
理解しようとして頑張っているので、親としてはじっくりと時間をかけて待つことが大切で、自分の力で理屈がつながるまで我慢していてほしいものです。
もしどうしても理解できなければ、子供のほうから「わからない部分」を聞いてきます。

私の場合も、親のほうが我慢できずいろいろと解説をしてきていました。
いくら説明を聞いても「頭の中での理解」が追いつかず、理屈をつなげようと思って一生懸命に考えているとさらに考え方まで教えてくれるのでそれが完全に仇。
整理できそうになっていた頭の中がいちど混乱してしまうと、また初めから考え直さないといけないので勉強を投げ出してしまうという悪循環に陥っていました。
発達障害があると、1つずつ理屈をつなげる作業に時間がかかります。
- しっかり時間をかけてやっと1つの理屈を理解する。
- 次につながる2つめの理屈を考え始める。
- 両方の理屈をつなげて全体を考える。
という具合に、少しずつ確実に理解しようと勉強を進めていきます。
発達障害の中学生が勉強しているときは、ぜったいに「効率」を求めてはいけません。不器用で時間がかかっても、少しずつ確実に理解させることが大切です。
親としての役目は、子供自身が勉強の理屈をわかるまで待つということが重要になります。
まとめ

今回は「発達障害の中学生が勉強できないときの原因と改善方法」について、グレーゾーンの経験をもとにお話ししてきました。
最後にまとめておきます。
- 家庭環境が良くない➝笑顔になる環境改善へ努める。
- 文字ばかりの教材を使っている➝イラストや映像授業などを取り入れる。
- 子供のペースを乱している➝余計な横槍を入れない。
ただしこの3つは、発達障害の中学生が勉強できない理由としておもな原因になります。
これらの原因を踏まえたうえで、ほかに勉強できない原因をしっかりと考えてあげることが「子供を想う親」の姿ではないかと私は強く感じます。
子供が勉強できない原因を、子供に向けてしまう親もかなり多くいると思います。
しかしそれは違って子供自身が原因となっているのではなく、親のほうが原因を作っていることのほうが間違いなく多く、親のほうこそ一刻も早く自分自身を振り返ってみることが必要ではないでしょうか。
グレーゾーンの経験からお話しした今回の内容を、ぜひ参考にしてみてください。
かならず3つのうちどれかの原因に「あっ‥!」と思われるのでは。