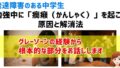発達障害とひとことで言っても程度や状態は様々で、発達障害の概念が幅広く子どもによって全然違います。
学校での勉強や宿題で苦労する子もいます。
勉強方法も一般的な勉強方法で学べる子もいれば、工夫が必要な子もいます。
ただ、本人に合う勉強法さえ見つかれば、発達障害由来の困難さや負担は軽減されます。
気が散りやすい子には
問題を○問解いたら休憩、10分やったら休憩などのように細切れで時間を区切ってみましょう。
1度に全部できなくても全く問題無しで、短時間に集中するのを繰り返し、最後に課題が終わっていればすべてOKです。
文章の読み取りのが苦手な子には
文章を読むのが苦手な子の中には、「耳で聞けば意味が分かるのに」という子がいます。
例えば国語で音読の宿題が出るのが辛い、算数で文章題になると途端に出来なくなるというケースです。
音読では「大人が一文ずつ読んで聞かせて、子どもが復唱する」方法だと、少し子どもは楽に読めることがあります。
文章題でも、大人が問題文を読み上げれば理解できる場合があります。
可能であれば大人が宿題に付き合う時間、というのを作ってみるのがおすすめです。
書くのが苦手な子には
字を整えて書くのが苦手、枠の中に収められない、鏡文字になる、画数が多い漢字を書き間違えるなど、書くのが苦手な子はたくさんいます。
問題の意味も考え方や答えも分かっているのに、書くのが苦手だと億劫になってしまいます。
紙とペンのアナログでは書けなくても、デジタルなら対応できるケースがあります。タブレットやキーボードを使って対応できるか、試してみる価値はあります。
タブレットでは文字を書く練習を楽しくできるアプリもあるので、子どもの反応を見ながら取り入れるのも1つの手です。
決まった流れで動くのが得意な子には
自閉スペクトラムなどの子は、1日の流れや手順が決まっていれば安心して動けるケースがあります。
宿題、お風呂、ご飯、自由時間、寝る時間など、学校から帰った後の行動を一定にすると、勉強にも取り組みやすくなるかもしれません。
ホワイトボードなどを使って1日の予定を事前に見せておけば、宿題にも取り組めます。
まとめ
いくつかの例をあげましたが、参考になれば幸いです。
デジタル教材を活用する、イヤーマフで雑音をシャットアウトする、タイマーで残り時間をカウントする、学習障害用トレーニング・アプリ![]() を取り入れる、100均知育グッズを使うなど、便利なものは溢れています。
を取り入れる、100均知育グッズを使うなど、便利なものは溢れています。
発達障害があっても、勉強を諦める必要はありません。
苦手なことは最低限だけ、楽にできる方法に置き換えて負担を軽くしてあげましょう。
本人が自信を持って大人になれるように、どんどん得意なことを伸ばしてあげてください。