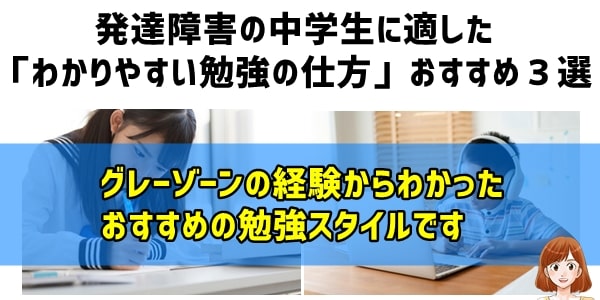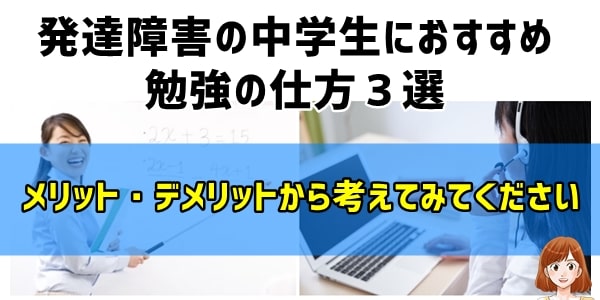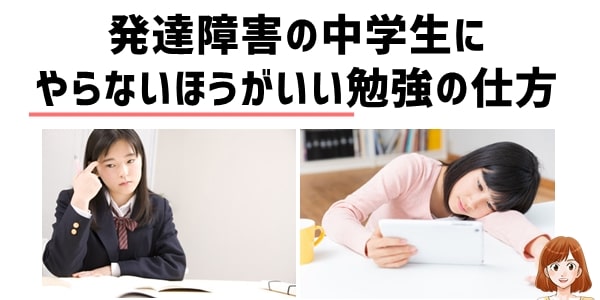こんにちはグレーゾーンのゆっきーです。
今回は「発達障害の中学生にベストな勉強の仕方が知りたい」という疑問に答えます。
私自身グレーゾーンの経験をもとに、ここでは発達障害の中学生に適した勉強の仕方として3つのパターンについて詳しく解説します。
いずれのパターンが正解ということはなく、家庭のスタイルに合わせて考えてみるといいかなと思います。
より効果的な勉強の仕方となるよう、いずれのパターンもメリット・デメリットを交え紹介します。
発達障害の中学生におすすめ勉強の仕方3選
ここでは「発達障害の中学生」に特化して、より効率的な勉強の仕方を3つ紹介します。
- 親がすべてサポート&アドバイス
- 通信教育(デジタル教材)の利用
- オンライン指導の利用
ぜひ家庭学習の場面を想像しながら、より最適なスタイルを選んでみてください。
![]()
勉強の仕方①親がすべてサポート&アドバイス
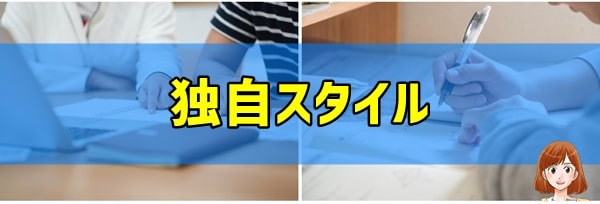
| 特徴 | 親が指導することで子供がもっとも安心しやすい勉強スタイル。教え方にしっかりと自信を持っている場合はかなりおすすめ。 | ||||
| メリット | ・子供が安心しやすい。 ・弱みを知っており対策しやすい。 ・費用を安く抑えられる。 | デメリット | ・勉強を教える能力が必要。 ・質問に答えられるだけの知識がいる。 ・間違った知識を教えてしまいやすい。 | ||

家庭学習の基本形ともいえるのが、この「独自スタイル」による勉強の仕方です。
もっとも簡単にスタートできて手っ取り早いので、多くの家庭ではこの勉強スタイルにとり組まれているのかなと。しかし小学生範囲が終わって中学生になると、なかなか親が教えることが難しいというのがネックになってくる場合も多くあります。
基本的に親が傍にいて教えるため子供は安心しやすい勉強の仕方ですが、簡単に始められるだけあってデメリットも多いもの。とくに苦手原因の追究をはじめ理解へつながる解説など、勉強の基本となる部分をしっかりと親がサポートできることが前提条件となります。
また発達障害の中学生へ勉強を教えるというのは、かなりの時間を見ておくことも必要。とくに1つずつ確実に理解しようとするのが発達障害の特性でもあるので、正しい順序で少しずつゆっくりと理解に時間をかけられることも必須条件となります。
親が正しくサポートできるだけの知識、および発達障害でも理解できるための豊富な時間。この2つが揃っていれば、こうした独自スタイルによる勉強の仕方もおすすめです。

グレーゾーンの経験から「超おすすめ」と感じる家庭学習教材をまとめています。個人スタイルで教える場合きっと助かる教材になると思います。
発達障害の中学生におすすめ「本当の意味で理解できる」家庭学習教材3選

勉強の仕方②通信教育(デジタル教材)の利用
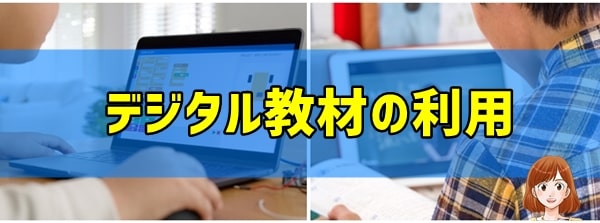
| 特徴 | 映像授業をはじめドリルやテスト機能など装備満載、基礎理解から定着までしっかりと家庭学習に盛り込むことが可能。ネット端末画面に慣れていれば学習効果バツグンでおすすめ。 | ||||
| メリット | ・映像授業で基礎学習しやすい。 ・演習問題が豊富。 ・楽しさを感じやすく継続率も高い。 ・費用がそこまで高くない。 ・ネット特性により情報量が多い。 | デメリット | ・端末画面に慣れていないと難しい。 ・子供任せスタイルは勧められない。 | ||

通信教育(とくにデジタル教材)は、私的に「発達障害へかなり適した勉強の仕方」と考えます。
とくに無学年方式が採用されているデジタル教材であれば、学力低下で以前の学年を復習させたいという場合に最適といえる学習方法。ほとんどの通信教育が現学年に最適化されているため、この「無学年方式」を選ぶことで発達障害で学力低下がみられる場合の悩み解消にもっとも適した勉強の仕方になると思います。
通信教育(デジタル教材)の大きなメリットとしては、まずもって「親の悩み解消」が挙げられます。
独自スタイルで勉強を教える場合には、教えるための学習知識をはじめ、過去のつまずき追及といったサポート力をもっていることが必須条件。これらがもし悩みであればデジタル教材がすべて補ってくれるので、親としては完全といえるまでにこの問題から解放される勉強の仕方になります。
デジタル教材に搭載される「映像授業」でしっかりと基礎理解ができ、さらに理解しやすいようわかりやすく解説されているため親の出番はなし。また「ドリル機能」など演習問題も豊富に搭載されているため、基礎理解のあと重要となる定着についてもしっかりカバーしてくれます。
ただ唯一のデメリットともいえるのが、ネット端末画面へ対する慣れの問題。パソコンやタブレット端末などに慣れていれば問題ないですが、画面を見ながら勉強できないという場合にはおすすめできない勉強の仕方になります。
独自スタイルで勉強を教えるのはリスクが大きいと考える場合は、このデジタル教材による勉強の仕方はかなり効果的で凝るいつに優れる手段になると私は感じます。

いろいろ体験して「いちばん理解しやすい」と感じたデジタル教材。無学年方式なので学力低下の見られる場合でもぴったりの家庭学習ができます。
発達障害のある中学生にすすめたい支援専門家監修のタブレット学習

勉強の仕方③オンライン指導の利用
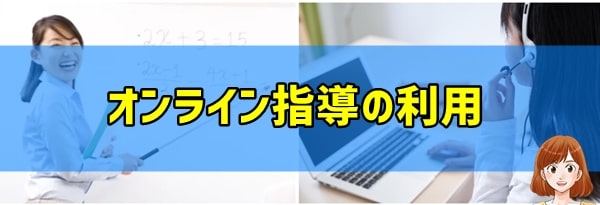
| 特徴 | マンツーマン指導で触接的に質問できるのでピンポイントな疑問解消親がしやすい。難関高校の受験にむけた対策としては極めて効果的。 | ||||
| メリット | ・自由に質問でき疑問解消しやすい。 ・対人関係に強くなりやすい。 ・高レベル学習にとり組める。 ・効果的な高校受験対策がしやすい。 | デメリット | ・対人が苦手であれば難しい。 ・重度障害の場合はお勧めでない。 ・やや費用が高い。 | ||

発達障害でもギフテッドの場合におすすめなのが、この「オンライン指導」という勉強の仕方です。
ギフテッドはいわゆる天才ともいわれる発達障害の症状で、一般的な基準よりもIQが高いというのがおもな特徴。したがって頭がよく回転し成績も高くなる場合が多いため、とくに難関私立高校へむけた受験勉強などに適したこのオンライン指導がおすすめといえる勉強の仕方になります。
オンライン指導の大きなメリットとなるのが、マンツーマン指導による疑問解消。まったく自由に質問ができるためピンポイントな疑問解消ができ、完全に親の出番はないといえる勉強の仕方になります。
とくに講師陣もかなり優秀で、難関私立高校をはじめトップレベルの国立大学在籍・出身者も多く存在するのがオンライン指導のメリット。
したがってどんな質問にも幅広く対応してくれるため、もちろん標準レベルの高校受験にもおすすめですが、とくにこの特性を活かした難関高校への対策として利用するのがベストといえる使い方になります。
ただ1点だけ問題点をいえば、子供自身に「積極性」があることがポイント。自分から疑問解消に向けて質問することができれば、これ以上なく適した問題解消方法はないと私は思います。

オンライン指導をいろいろ体験&電話確認して「絶対に選んで失敗しない」と思えたベスト3選です。かなり安心して利用できると思います。
発達障害の中学生におすすめ「5教科オンライン授業」ベスト3選
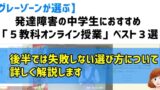
発達障害の中学生にやらないほうがいい勉強の仕方
私としては、つぎの3つに注意すべきと考えます。
- 理解できていない根本的な原因を放置する
- 正しくない順序で解説をする
- 子供の反応を見ないまま先へ進む
発達障害の特性をいろいろ考慮すると、かなり気を付けるべきポイント。
さらに詳しく、これら3つの注意点について解説します。
理解できていない根本的な原因を放置する

発達障害の中学生において、ほぼ無意味となる恐れがある勉強の仕方です。
たとえば足し算の理屈が理解できていない場合、いくら2桁の足し算を教えようとしてもまったく理解できないというのがよい例。まずもって5教科すべてにおいて、根本的な理屈についてしっかりと教えることから始める必要があります。
とくに親が仕事などで忙しく、家庭学習につきあう時間的余裕が少ない場合などに起こりやすいパターン。なんで理解できないのかと子供を責めるばかりで、根本的な問題解消へつながっていない状態のため、かなり勉強の仕方における要注意ポイントといえます。
もし現時点で勉強している内容が理解できていないようであれば、根本的につまずいている原因(分野・単元)はどこにあるかを徹底追及。しっかりと原因となっている箇所までさかのぼって、根底部分を理解できるよう教えることが問題解決の糸口になります。
またこの問題を放置するほど、子供自身としては勉強をどんどん「嫌い」になっていく恐れも考えられます。思った以上に大変になる将来が待っているので、少しでも早くこの問題に気付いて対処・改善することをおすすめします。
正しくない順序で解説をする

親として気づきにくいポイントとして、まずもってこの「間違った順序」が挙げられます。
たとえば算数・数学を教えるときは単元を分割して、順序良く1つずつ理解させることが重要。しかし順序が逆にあったりすると、たちまち理解できず子供は迷宮入りしてしまうという問題です。
とくに親が教えるスタイルではこの問題が起こりがちで、親自身も気づきにくいため問題解決がかなり難しいポイント。まずは親のほうが正しい順序を理解して、そのうえで子供へ教えることが重要になります。
また教える順序が乱れることのほかに、言葉が飛んでしまうことにも注意が必要。言わなくてもわかるような言葉を飛ばしてしまうことで、とくに発達障害の中学生にとっては致命的ともいえる理解不足へつながりやすいものです。
したがってまずは教える順序を正しくな食べる、さらに言葉足らずについて十分考慮することが大切。発達障害の特性から考えても「少しでも理解できないと投げ出してしまう」ことが考えられるので、独自スタイルで教えるときはとくに注意すべき間違った勉強の仕方になります。
もしこの問題をスムーズに解消するのであれば、親が教えるというリスクを避けて、通信教育(デジタル教材)の映像授業に解説を任せるなどの勉強方法をとるのがおすすめです。
子供の反応を見ないまま先へ進む

とくに健常児と発達障害の子供がいる場合には、この問題に目を向けておくことが重要であると私は思います。
同じように勉強を教えても、発達障害がある子供は理解しきれないもの。まずもって理解の仕方がゆっくりで、1つずつ少しずつ理解していくという特性があるのでこの辺りも考慮する必要があります。
私自身もグレーゾーンですが、この問題でかなり引っかかって勉強が進まない時期もありました。親のほうは一生懸命に教えてくれていても、私自身の理解が追い付かず説明だけが先に進んでしまい、結果的に成績アップもせず勉強を嫌になるだけという状況が多々あったものです。
この問題を解消するためには、まず親のほうが子供の状態をしっかりと把握すること。完全に理解できていることを確認して、もし何なら「子供に解説させてみる」という行動を交えながら先へ進むことが大切。
また親のほうが圧力をかけてしまうと子供は「わかったふり」をする場合もあるので、いくら教える時間が少ない場合でも圧力をかけることなく確実に理解させることだけを考えるのが重要です。
とくに発達障害があって学力低下がみられる場合には、親が圧力をかけることでより委縮してしまいがち。くれぐれも「ゆっくり理解しよう」というスタンスをもって、子供のペースに合わせて進めていくという勉強の仕方が求められます。
まとめ

今回は「発達障害の中学生にベストな勉強の仕方が知りたい」という疑問にたいして、グレーゾーンの経験からわかった勉強の仕方3選をはじめ、発達障害の中学生にやらないほうがいい勉強の仕方という角度から答えてきました。
グレーゾーンの私自身も、これまでに勉強の仕方でかなり苦労してきました。
基本的には親が教えてくれるスタイルでしたが、どうしても親との「歩幅」が揃わず勉強を嫌いになるというマイナス結果。もっとも適していた勉強の仕方は、自分自身のペースで実践できる「デジタル教材」だったと強く感じています。
その頃のデジタル教材はそこまで高性能ではなく、まだAIシステムなどもほぼ搭載されていない時期。しかし自分の意志で勉強を進められるという意味においては、かなり助かったと感じる勉強の仕方です。
さらに現在のデジタル教材はかなり進歩しており、最新鋭のAIシステムをはじめ理解しやすい映像授業なども標準装備。しかも豊富な演習問題なども搭載されているので、発達障害の中学生にとってはこれ以上ない効率的な勉強の仕方になると思います。
もちろん各家庭によって勉強の仕方は異なり、より好みや考え方に沿ったスタイルがあると思います。ぜひ私が提案してきた3つの勉強スタイルから、ぴったりと合った勉強の仕方を選んでみてください。