
発達障害のある中学生は、じっと座って勉強することが難しい場合があります。そのため「歩きながら勉強する=歩き勉強」を取り入れるご家庭も増えています。
しかし「危険ではないか?」「本当に効果があるのか?」と不安を感じる方も多いはず。
本記事では、歩き勉強のメリットとリスクを整理し、発達障害の特性を活かした安全な工夫をご紹介します。
歩き勉強とは?発達障害の中学生に注目される理由


発達障害の中学生にとって「歩き勉強」は、歩きながら学ぶことで体を動かす欲求を満たしつつ集中力を維持できるという点が評価されています。
ここでは、なぜ歩き勉強が発達障害の中学生に向いているのかを詳しく見ていきます。
座って勉強できない子どもに向くスタイル
- 歩くことで体の緊張がほぐれ、勉強に取り組みやすくなる
- 「動いてもいい」という安心感が学習意欲を高める
- 座ることへの苦手意識を軽減し、家庭学習の継続性が増す

発達障害の中学生の中には、多動傾向や落ち着きのなさから長時間座ることが難しいケースがあります。無理に座らせようとするとストレスが増え、逆に学習意欲を削いでしまうことも少なくありません。
歩き勉強は「座れないこと」を前提に工夫するスタイルであり、自然な動きを取り入れることで勉強を続けやすくなります。
動きながら学ぶと集中力が続く仕組み
歩き勉強が発達障害の中学生に適している背景には、脳の働きが関係しています。

人は歩くことで血流が良くなり、前頭葉が活性化します。その結果、集中力や記憶力が高まる可能性があります。
特に暗記科目に取組む際には、歩きながらリズムよく音読することで効率的に学習が進みやすくなります。
また、歩きながら学ぶと「飽き」が来にくく、短時間で切り替えを行いながら勉強を継続できる点も強みです。座学で集中が続かない子どもにとって、歩き勉強は現実的な学習スタイルとなり得ます。
歩き勉強のメリットと効果
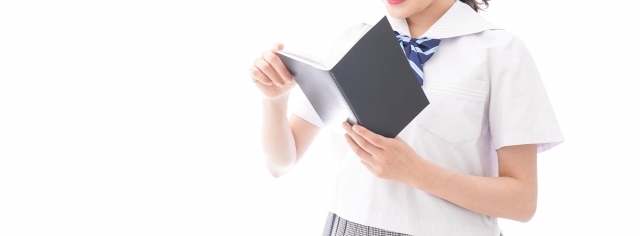

歩き勉強は「集中できる環境を作りたい」と考える発達障害の中学生にとって有効な方法です。ここでは、その具体的なメリットと効果を整理してご紹介します。
記憶定着率が上がる可能性
歩きながら暗記カードを使ったり、教科書の要点を音読したりすると、動きと学習内容が結びつきやすくなります。
脳は運動と情報を同時に処理するため、ただ座って読んでいるよりも記憶に残りやすいと言われています。
| 学習方法 | 記憶の定着度 | 特長 |
|---|---|---|
| 座って音読 | 中程度 | 落ち着いた環境で取り組める |
| 歩きながら音読 | 高い | リズムと動きで記憶が定着しやすい |
| 歩きながら暗記カード | 非常に高い | 短時間で反復しやすい |
多動性や落ち着きにくさの解消につながる
- 体を動かすことで不安感やストレスが軽減される
- 「動いてもよい」という環境が安心感を与える
- 家庭学習の拒否感が減り、勉強時間を確保しやすくなる

発達障害の中学生が持つ「じっとしていられない」という特性を無理に抑え込むのではなく、歩き勉強として学習に取り入れることでポジティブに活かすことができます。
体を動かしながら勉強することで落ち着きを取り戻しやすくなり、結果的に学習効率が向上するケースも多く見られます。
テスト勉強での実際の活用事例
実際に歩き勉強を取り入れた発達障害の中学生の事例では、特に暗記が中心となる社会や理科の学習に効果を発揮しています。

例えば、暗記カードを片手に廊下を往復しながら答えを声に出して確認する方法や、録音した英単語を聞きながら部屋を歩く方法などが効果的です。
保護者のサポートとしては、安全に歩けるスペースを確保することや、短い時間で区切って学習を続ける工夫が重要。こうした方法を組み合わせることでテスト勉強に対する不安を軽減し、結果として学力向上にもつながります。
歩き勉強のリスクと危険性
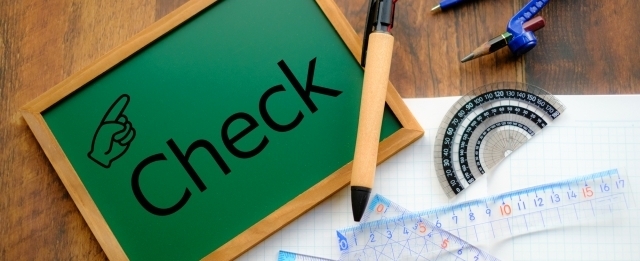

発達障害の中学生に歩き勉強を取り入れる場合、効果だけでなくリスクも考慮する必要があります。
ここでは、転倒や事故などの物理的リスク、家庭や周囲とのトラブル、そして勉強効率が下がる可能性について詳しく解説します。
転倒・事故など物理的なリスク
歩き勉強は体を動かしながら学ぶため、転倒や家具にぶつかるなどの物理的リスクが伴います。
特に廊下や狭い室内で行う場合は注意が必要です。
- 家具や電化製品にぶつかる可能性
- 滑りやすい床での転倒リスク
- 小物やペットに足を引っ掛ける事故
安全面を確保するため、広めのスペースを選び、周囲の障害物を片付けることが重要です。
家族や周囲とのトラブル(音や動線)

発達障害の中学生が歩き勉強をすると、音や動きが家庭内の他のメンバーの作業や睡眠に影響することがあります。
また、廊下やリビングの移動は家族の生活動線とぶつかりやすく、トラブルの原因になる場合があります。
- 歩きながらの音読で他の家族が集中できない
- 生活動線に人がいるとぶつかる可能性
- 共有スペースでの学習は周囲のストレスになり得る
勉強効率が下がるケース
歩き勉強は集中力を高める効果がありますが、逆に注意力が散漫になる場合もあります。

歩くことに気を取られすぎると、暗記や理解に集中できないことがあるため、勉強内容と方法を工夫することが大切です。
- 歩くこと自体に意識が向いてしまい暗記がおろそかになる
- 長時間歩き続けることで疲労し、学習効率が低下する
- 教材やカードの管理が難しくなる場合がある
安全に取り入れる工夫


発達障害の中学生に歩き勉強を取り入れる際は、安全面と学習効率を両立させる工夫が必要。ここでは環境づくり、勉強内容の工夫、座る時間との組み合わせ方法について解説します。
歩きやすい環境づくり(室内・廊下・マット敷き)
安全に歩き勉強を行うためには、移動する空間の環境整備が欠かせません。
家具や小物を片付け、滑りにくいマットを敷くことで転倒リスクを減らせます。
- 広めの廊下や空きスペースを確保
- カーペットや滑り止めマットを設置
- 机・椅子・電化製品などの障害物を移動
勉強内容を工夫(暗記カード・音読・録音活用)
歩き勉強では教材や学習方法を工夫することで、学習効率を高められます。
暗記カードや音読、録音教材を活用することで、歩きながらでも集中して学習できる環境を作ることが可能です。
| 方法 | 活用例 | メリット |
|---|---|---|
| 暗記カード | 廊下を往復しながら答え合わせ | 短時間で反復学習可能、記憶定着率向上 |
| 音読 | 歩きながら教科書や要点を声に出す | 発音や理解力を同時に強化 |
| 録音教材 | 英単語や用語を聞きながら歩く | 耳で学ぶため、体の動きと学習を連動 |
歩く時間と座る時間を組み合わせる方法
歩き勉強だけでなく、座学も組み合わせることで学習効果を最大化できます。
短時間ずつ歩く時間と座る時間を切り替えることで、疲労や注意散漫を防ぎつつ、効率的に勉強を進められます。
- 20分歩き+10分座学を1セットにして計画する
- 疲れたときは座学に切り替え、無理に歩かせない
- 暗記や復習は歩き勉強、問題演習は座学など使い分ける
家庭学習に役立つサービスの紹介
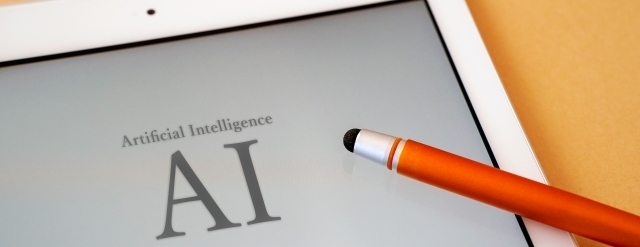

発達障害のある中学生が歩き勉強を取り入れつつ効率的に学習するためには、家庭での学習環境をサポートするサービスの活用が有効です。
特にオンライン学習サポートは、自宅で集中できる環境を提供しつつ、発達障害の特性に応じた学習方法を提案してくれます。
発達障害専門のオンライン学習サポート


サイト内でおすすめしているサービスを利用すると、家庭学習における悩みを解消し、歩き勉強と併用して学習習慣を定着させやすくなります。
子供の理解度に合わせたカリキュラムや、学習進捗のアドバイスを受けられる点も大きなメリットです。
| サービス名 | 対象 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| すらら | 発達障害の中学生全般 | 映像教材と個別フォローで歩き勉強と併用可能 |
| スタディサプリ中学講座 | 注意欠陥・多動傾向の中学生 | 短時間集中型カリキュラムで効率よく学習 |
| オンライン家庭教師ガンバ | 学習の遅れが気になる中学生 | 個別指導・進捗管理機能で家庭学習を可視化 |

これらのサービスを活用することで、発達障害の中学生が歩き勉強を行いながら、無理なく学習習慣を定着させることができます。
特に座ることが苦手な場合でも、オンライン教材を使って歩きながら学ぶ方法を取り入れることで、効率的に知識を定着させることが可能です。
まとめ

発達障害の中学生にとって、歩き勉強は座学だけでは得られない集中力や記憶の定着をサポートする学習方法です。
ただし、転倒や家庭内トラブル、学習効率低下などのリスクもあるため、安全な環境づくりや学習内容の工夫が必要。
また、サイト内で紹介している発達障害専門のオンライン学習サポートを併用することで、家庭での学習をより効果的に進められます。
歩き勉強を上手に取り入れ、安全かつ効率的な学習環境を整えてあげることが、中学生の学力向上と学習習慣定着につながります。



